変化の中で働き続けるということ。学研メディカルサポートで見た両立のロールモデル
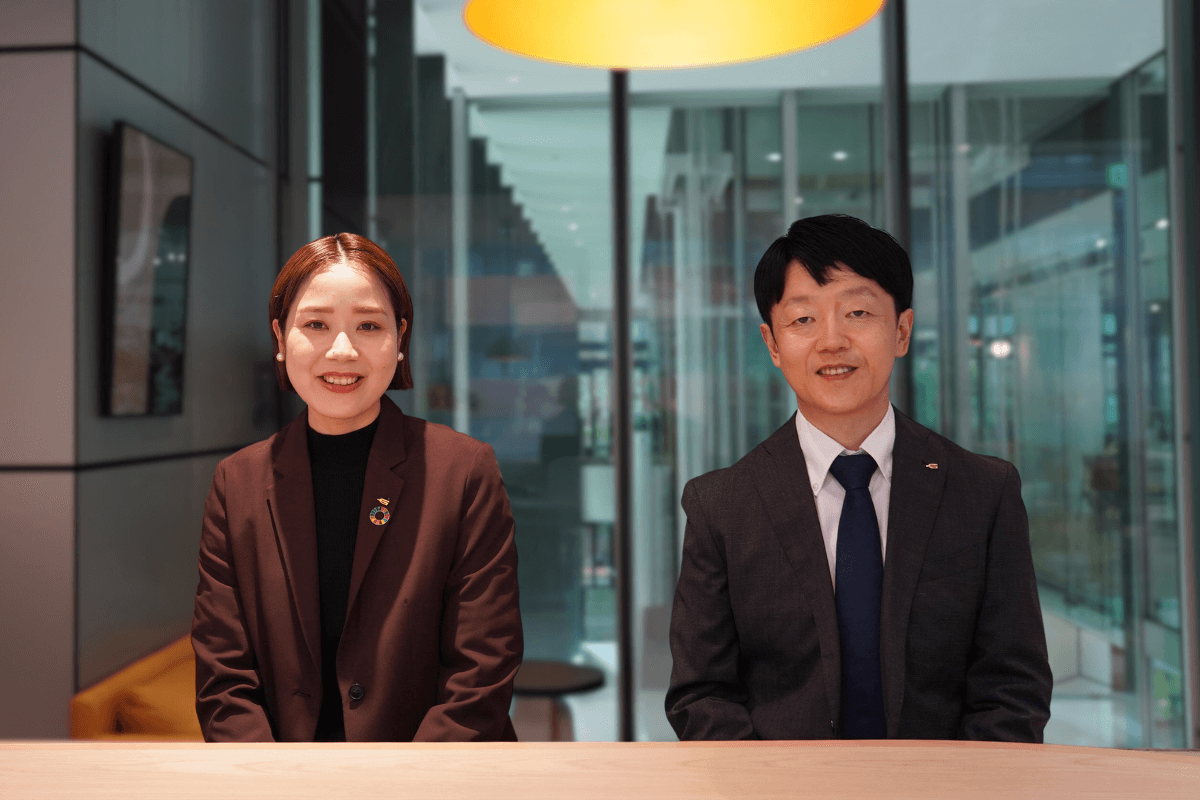
「急な発熱」「終わらない仕事」「止まらない悪阻」。
仕事と妊娠・子育ての両立の現場では、想定外の“できない瞬間”が、いつも突然やってきます。
そんな時、「どうしたらできるか」を一緒に考えてくれる仲間や上司がいる。その存在こそが、働く親にとっていちばんの支えになるのかもしれません。
株式会社学研メディカルサポートでは、在宅勤務や育児休業制度の柔軟な運用を進め、2025年2月に「子育てサポート企業」としてくるみん認定を取得。
制度だけに頼らず、社員一人ひとりの声に耳を傾け、柔軟に動く企業文化を育んできました。
今回は、繁忙期に育休を取得したシステムエンジニアのFさんと、妊娠中の悪阻をきっかけに特例的な在宅勤務へ切り替えたKさんに、ライフステージの変化と両立のリアルを伺いました。
(2025年9月取材)
※お話を伺ったお二人のお名前は、プライバシー保護のためイニシャルで表記しています。
目次
プロフィール

Fさん(写真右)
システムエンジニア/制作部 副部長
2児の父。1人目のお子さんで約2ヶ月、2人目では3ヶ月の育休を取得。現在はフルタイムで勤務しながら、夫婦で協力して子育てに奮闘中。
Kさん(写真中央)
経理/管理部 債権管理課 課長代理
1児の母。妊娠中の悪阻をきっかけに、週5日在宅勤務へ切り替え。インタビュー時は復職後4ヵ月。時短勤務でマネジメントや業務改善にも取り組む。
山中 泰子(写真左)
株式会社QOOLキャリア代表取締役社長
インタビュアー。企業の制度と個人の働き方を結ぶ視点から、1児の母である自身の経験も交えながら、お二人のエピソードを掘り下げる。
繁忙期の育休取得と「パパになる時間」の葛藤
――育休を取得された時の同僚や上司の方の協力をどう感じましたか?
Fさん:長女も次女も、ちょうど当社の繁忙期である2月と3月に生まれました。 正直、「この時期に休むなんて大丈夫かな」という迷いはありました。でも、「今しかできない経験だから」と周囲の人たちが背中を押してくれたこともあり、 結果的に長女のときは約2ヶ月 、次女のときは約3ヶ月の育休を取りました。
事前に引き継ぎは進めていたものの、2人目のときは出産が予定より2週間早まって「明日生まれるよ」という連絡が急に届いた時は本当に焦りました。あの日は「今日中にできることは全部片づけなきゃ」と必死で動いたんですが、頭の中は正直バタバタでしたね。
そんな中でも、メンバーたちは落ち着いて対応してくれて、細かいことを気にせず仕事を引き継いでくれました。子育て中のメンバーがチーム内にいなかったこともあり、前例がほとんどない中での育休でしたが、自分が戸惑っている分、周りの柔軟さに本当に助けられました。

――実際に育休を取得されて、どのような変化がありましたか?
Fさん: 育休で家庭に専念できたのは良かったんですが、最初のうちは思っていたようにはいきませんでした。
家事や育児の負担が妻に集中してしまったときもあり、気づけば妻も私も余裕がなくなっていて。 寝不足のまま育児や家事をこなす日が続き 、会話も減って、ちょっとピリッとした空気になることもありました。
「このままじゃダメだな」と思って、家のことを一つずつ見直していきました。どんなに忙しくても、自分が担当する家事を決めてやりきるようにしたり、少しでも妻の負担を減らせるように意識して動きました。親は遠方に住んでいるので普段はなかなか頼れませんが、本当に大変なときは、迷わずヘルプをお願いするようにしています。ひとりで抱え込みすぎず、親や周りのサポートを借りながら、家庭のリズムを整えていく中で、会社の理解や仕組みの柔軟さにも助けられました。
制度を超えた柔軟な対応
――そうした変化の中で、困ったときに会社からどんなサポートがありましたか
Fさん:保育園の定員に空きがなく、妻が復職できない時期がありました。どうすればいいか悩んでいたところ、自宅近くの認可外の企業主導型保育施設に空きが見つかったんです。
まだ当社とは未契約の施設だったので、管理部に相談してみました。するとすぐに契約を進めてくれて、妻も認可保育園の空きを待たずに復職できました。妻が「そんなに早く対応してくれるの?」と驚くほどのスピードでした。
こうした対応に限らず、当社では一人ひとりの状況に合わせて柔軟に考えてくれる姿勢があります。管理部も「まずやってみよう」と動いてくれるので、決まった仕組みだけではなく、その時々に新しいサポートが生まれていくような感覚があります。
困ったときに相談できる環境があるのは、とても心強いです。
Kさん:私の場合は妊娠中は匂いからくる悪阻(つわり)がひどくて、書類の紙やペンのインクの匂いにも反応してしまうほど辛い時期がありました。当時は出社するのも大変で、通常通りに働くのが難しくなってしまったんです。
通常、週2回在宅勤務があるため、それを利用していましたが、それでも厳しい日が続いていました。 思い切って社長や上長に相談したら、「無理せず続けられるように」と、週5日の在宅勤務への切り替えを許可されたんです。制度上、在宅勤務は週2回まででしたが、特例としてすぐに判断をしてもらえて、なんとか仕事を続けることができました。出社が必要な業務は他のメンバーがカバーしてくれて、本当に助かりました。
いま振り返ると、あのとき無理せず相談して柔軟に判断してもらえたからこそ、今もこうして働き続けられているのだと思います。
山中:制度があるだけじゃなくて、ちゃんと「どう動けるか」を考えてくれるんですね。そういう人がいる職場って、やっぱり安心して声を上げやすいですよね。
お二人は普段の業務でも関わることがあるんですか?
Kさん: 直接関わることは、実はあまりないんです。
でも妊娠中に 、Fさんが気にかけて声をかけてくれました。保育園の情報まで調べて共有してくれたのがすごくうれしかったです。部署が違っても、気にかけてくれる人がいるのは心強いなと思いました。
Fさん: もともと調べるのが好きなんですよ(笑)。自分の経験もあったので、「これ役立つかも」と思ってつい動いちゃうんです。お互いに助け合える雰囲気が自然にある気がします。

限られた時間で成果を出す「集中力」の向上
――ライフステージの変化を経て、ご自身の働き方や仕事への向き合い方はどのように変わりましたか?
Fさん:時間の制約があるからこそ、集中して動けるようになったと感じています。残業をしない日を決めて「子どもが起きているうちに帰る」と、時間を意識的に区切るようになりました。朝はどうしてもバタバタしますが、限られた時間でも家族で朝ごはんを囲むようにしています。短い時間でも顔を合わせて話すことで気持ちのスイッチが入り、仕事への集中力も高まります。
在宅勤務も活用し、妻が長女を保育園に送る間は、まだ入園していなかった次女を自宅で見ていました。家庭の状況に合わせて働ける柔軟さがあることで、安心して仕事にも向き合えています。
時間の終わりが決まっているからこそ、「ここまでに終わらせる」という意識が自然に強くなり、優先順位を見極めて動く力も、家庭での経験を通して磨かれたと感じています。
Kさん: 復職して4か月ほどですが、今も試行錯誤の毎日です。
9時から16時の時短勤務に切り替えて、残業をしないように業務時間内で調整していますが、最初のうちは時間が足りず、思うように仕事が進まないこともありました。正直、もどかしさや周囲への申し訳なさを感じる瞬間は、今でもあります。
それでも続けていくうちに、限られた時間でどう動くかを考える力が少しずつついてきたように思います。優先順位をつけるスピードが格段に上がり、他のメンバーにも業務の棚卸しをお願いしながら、チーム全体の動きを見直すようになりました。今は、プレイヤーとしての仕事は他のメンバーに任せて、マネジメント業務や課内の業務改善、業務分担の見直しに注力しています。
子どもの急な体調不良などで予定が変わっても、焦らずリカバリーできるようになったのは、両立の中で鍛えられた力だと思います。
「限られた時間でもやれる」と思える瞬間も徐々に増えてきました。

社員の声にすぐ応える会社の「近さ」
――社員が安心して働ける背景には、どんな職場の雰囲気があると思いますか?
Fさん:弊社の代表は、社員の働き方に対する理解が非常に柔軟です。子どもがいても、無理なく長く働けるようにという考えが根底にあって、そうした姿勢があるからこそ制度も使いやすいんだと思います。
Kさん:オフィスの入口近くの席に代表が座っていることが多いので 、朝の挨拶から自然と会話が生まれていますね。育休中の社員のことも全員覚えていて、積極的に話しかけている様子が見てとれます。社員一人ひとりにちゃんと目を向けてくれているんだなと感じますし、その空気が社内全体に広がっていて、話しかけやすい雰囲気が自然にできている気がします。
管理部:代表の日ごろのコミュニケーションが、会社全体の「声を拾う姿勢」につながっていると思います。現場で出た意見や困りごとに対して「まずやってみよう」と動くことが多く、そこから新しい制度や運用の形が生まれてきました。
そうした一つひとつの積み重ねが、「くるみん認定」につながったと感じています。もともと学研グループ全体で子育て支援を進めている取り組みではありますが、学研メディカルサポートらしい現場の柔軟さが評価された結果だと思います。

山中:トップが社員と近い距離で話してくれると、現場の声がちゃんと届くんですね。制度を整えるだけじゃなくて、「どうしたらもっと働きやすくなるか」をみんなで考えているように感じます。
Kさん:私自身も、社員の声から生まれた会社のベビーシッター利用補助を使っています。子供が体調不良で保育園を休むことになったときに、ベビーシッターさんに家で子供を見てもらい、別室で仕事をすることができて 、本当に助かっています。
「困ったときは頼っていい」と思える仕組みがあるのは、すごく心強いです。
未来の両立を考える人へのメッセージ
――今後、仕事と子育ての両立を目指す社員や、悩んでいる方々へメッセージをお願いします。
Fさん: 「相談する」ことがとても大事だと思っています。
話してみるだけで、気持ちが少し軽くなることってありますし、何より、発言したことでマイナスになることは本当にひとつもないんです。
当社の場合、相談したことがきっかけで制度が見直されたり、新しい仕組みができたりすることもあって、ちゃんと声を受け止めてくれる人がいる。そういう環境がありがたいなと思っています。
勇気がいることかもしれませんが、「これ、言ってもいいのかな」と思ったとき、自分の中で決めつけずに、その気持ちのまま口に出してみることだけでも一歩だと思います。思っているより、ちゃんと聞いてくれる人はいますよ。
Kさん: 私自身も現在進行形で模索中ですし、悩みながら進んでいるのが現実です。「これでいいのかな」と思う日もありますが、自分だけで抱えこむと、きっと続けるのが苦しくなってしまうと思います。ベビーシッターのような外部サービス や、同僚やパートナーに相談したり、仕事でも家庭でも「話せる人」を持つことが大事だと感じています。
無理しすぎず、自分のやれる範囲で頑張って、周りに相談しながら進められると良いのかなと思います。「ヘルプ」を出すことが、結果的に続ける力になるんだと思います。
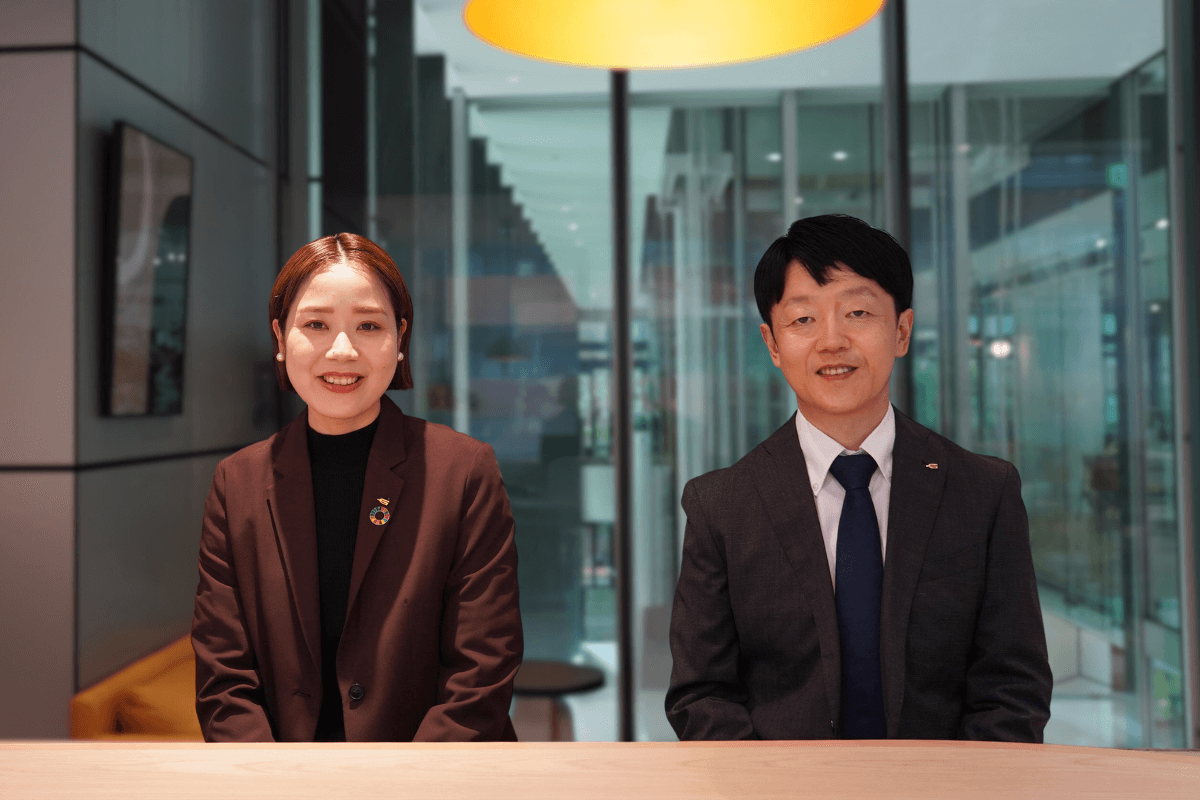
編集後記
仕事と子育ての両立は、「こうすればうまくいく」という形があるわけではないと思います。時短勤務だから大変とか、子どもが小さいから仕方ないなど、ひとくくりにできるものでもありません。
家庭の事情も、体調も、サポートしてくれる人の数も、それぞれ違う。
だからこそ、「誰かがちゃんと見てくれている」という安心感が、働き続ける力になるのだと感じます。
取材の中では、FさんやKさんの言葉の端々から、人事や上司への深い信頼が伝わってきました。困ったときにすぐ相談できて、その声を受け取った人が「どうにかしよう」と動いてくれる。
そして、管理部の方も「使ってもらえてうれしい」と話していたのが印象的でした。
そんなやりとりが自然に交わされていることが、学研メディカルサポートの働きやすさを支えるいちばんの強さだと思います。
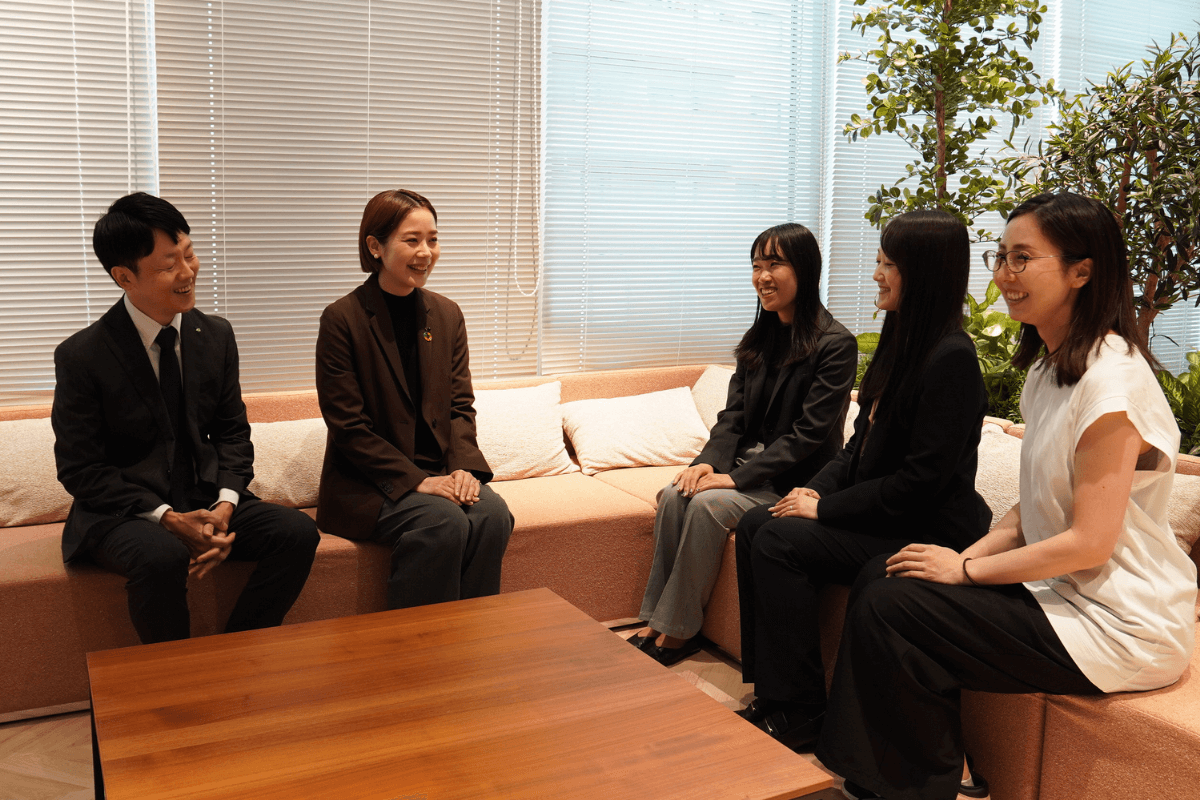
会社紹介:学研メディカルサポート
株式会社学研メディカルサポートは、学研グループの一員として、医療・看護分野の教育支援活動を中核とし、 人と社会の“学び”を支える企業です。
eラーニングをはじめとした医療従事者向けの教育コンテンツを提供しており、 現場で働く人のスキルアップとキャリア形成を支援しています。
働く社員の健康と成長にも力を注ぎ、在宅勤務制度やカフェテリアプランなど柔軟な制度運用を推進。
2025年には「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」に5年連続 で認定され、同年2月 には「子育てサポート企業(くるみん認定)」も取得しました。
制度を整えるだけでなく、学び合い支え合う企業文化を育みながら、2026年には設立15周年を迎えます。
企業公式HP:https://gakken-meds.jp/
ライフステージサポート「TUMUGU(つむぐ)」のご紹介
QOOLキャリアは、女性のキャリアに留まらず全ての人がワーク・ライフ・シナジーを追求できる社会の実現を目指し活動しています。
働きがいをアップデートする福利厚生サービス「TUMUGU(ツムグ)」では、専門家へのLINE相談、医師に直接質問ができるQ&Aサービス、ヘルスリテラシー向上セミナー、ライフステージサポートサービスの割引特典を提供しています。
TUMUGUのサービスサイトはこちら:https://tumugu-service.jp/
お問い合わせはこちら:https://career.qo-ol.jp/tumugu/



