ライフステージの変化はキャリアの停滞じゃない。セミナーインフォ瀬川真梨子さんと会社が共に創る、自分らしい働き方とは
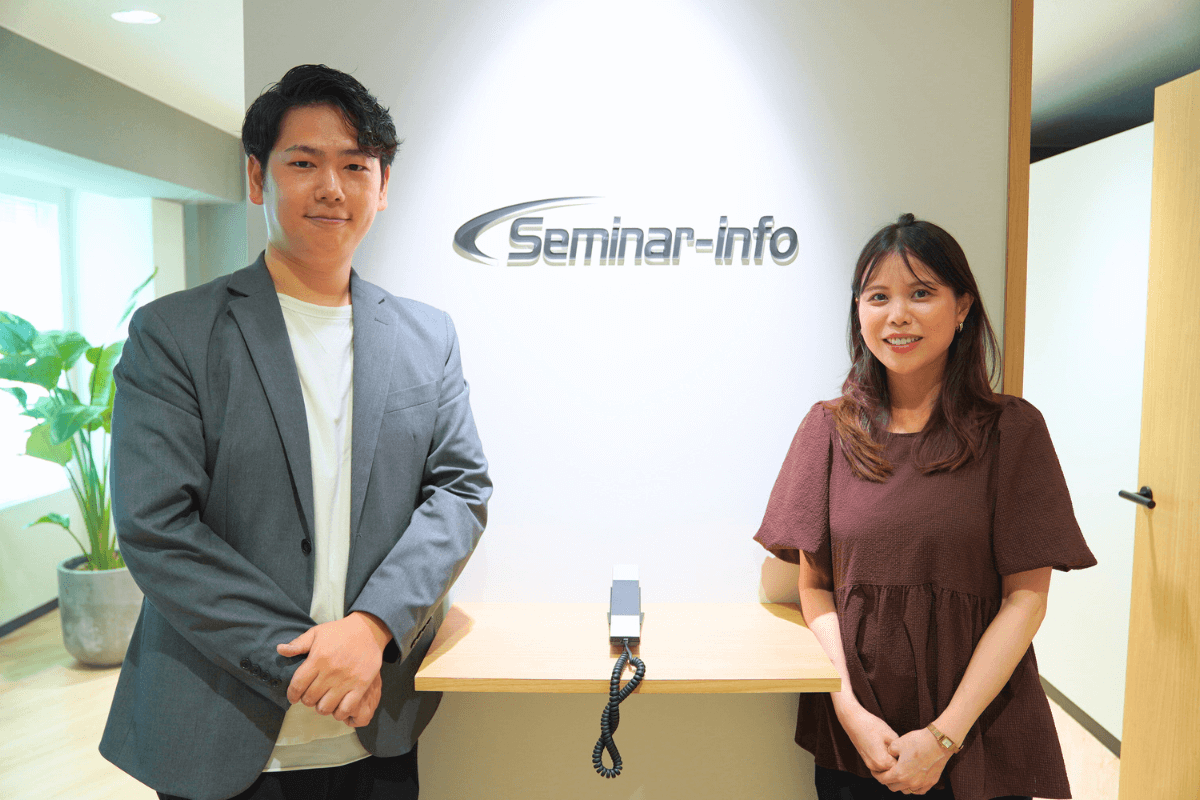
「育児でキャリアが中断してしまう」「急な休みで迷惑をかけるのが心苦しい」。ライフステージの変化に直面した多くの女性がそんな悩みを抱えています。しかし、株式会社セミナーインフォには、出産・育児という大きな変化を乗り越え、むしろキャリアを加速させている社員がいます。
今回お話を伺ったのは、DE&I(多様性・公平性・包括性)を主軸とした動画メディア『PLACEY』を率いる瀬川真梨子さんと、プロモーショングループディレクターの松尾真央さん。
瀬川さんは産後9か月で復職し、新規事業推進部に異動しリーダーに就任。本人の努力に加え、社員の声を生かして制度を磨く文化と、上司の伴走が大きな力となりました。
仕事と家庭の両立のリアル、マネジメントの秘訣を通して「誰もが働きやすい環境」を考えます。
(2025年9月取材)
目次
プロフィール紹介
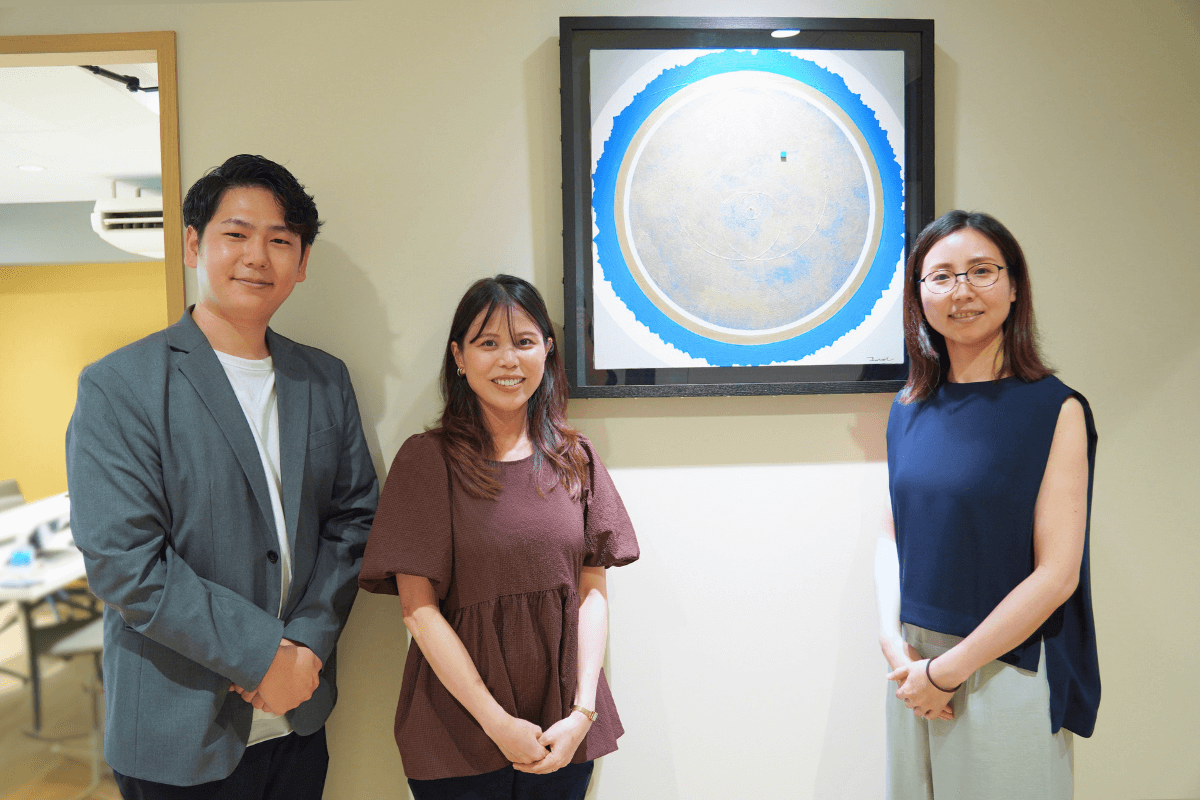
瀬川 真梨子(せがわ まりこ)さん(写真中央)
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ / PLACEY事業プロジェクトリーダー
大学卒業後、航空業界で客室乗務職と地上業務職の両方を経験したのち、大手クレジットカード会社でtoCマーケティングを担当。2020年にセミナーインフォへ入社し、産育休を経て復職後は、DE&Iをテーマにした動画メディア『PLACEY』の立ち上げをリード。現在は2歳の子どもの育児と仕事を両立しながら、新たな働き方を実践している。
松尾 真央(まつお なお)さん(写真左)
株式会社セミナーインフォ プロモーショングループディレクター
大学卒業後、大手ブライダル会社を経て2017年にセミナーインフォ入社。営業職として活躍後、セールスグループディレクター、新規事業開発ディレクターを歴任し、2024年11月より現職。現在は4つのユニットを率い、メンバーのキャリア形成にも尽力している。
山中 泰子(やまなか やすこ)(インタビュアー)(写真右)
株式会社QOOLキャリア 代表取締役社長
大手IT系人材サービス会社で人事として、採用・育成・制度設計等を経験。自治体と共にひとり親家庭の就業支援事業を立ち上げ、託児所を併設した就業施設の開設・運営に携わる。その後、上場会社の人事担当執行役員、スタートアップ企業の人事責任者を経て、2022年4月からQOOLキャリアで代表に就任。1児の母である自らの経験も活かし、キャリアアドバイザーとして仕事と育児の両立に悩む女性のキャリア支援も行う。
産後9ヶ月での早期復職。大きな不安をどう乗り越えたのか
――瀬川さんは、お子さんが生後8ヶ月の時に復職されたそうですね。とても早い決断ですが、背景にはどんな想いがあったのでしょうか?
瀬川さん(以下敬称略):もともと仕事が好きで、キャリアにブランクを作りたくないという焦りのような気持ちがありました。それに加え、産後1ヶ月で実母が他界し、誰にも頼れず孤独を感じていた時期でもありました。社会との繋がりを取り戻したい、仕事を通じて自分らしさを保ちたいという想いが強かったんです。保活激戦区のため1歳児で預けられないリスクも考え、保育園を15件ほど見学し、丹念に情報収集をして、0歳児でも安心して預けられる環境・雰囲気だと感じた保育園に預けられることが決まったのが大きな一歩でした。
――0歳児を抱えての復職は不安も大きかったと思います。特に何が一番の課題でしたか?
瀬川:「慣れない育児と仕事の両立」そのものが大きな課題でした。子どもが第一優先になる中で、時間的な制約が生まれますし、両家の実家も遠方で周囲のサポートを得にくい状況でした。特に0歳児は頻繁に体調を崩すので、急なお迎え要請にどう備えるかで常に頭を悩ませていましたね。復職後も夜間授乳を続けていたので、睡眠不足も重なり振り返ると身体的にもハードでした。

――そんな状況で、心を支えになったものは何だったのでしょうか?
瀬川:仕事に復帰したことで、「社会人としての自分」と「母親としての自分」という2つの役割を持てたことが、結果的に心のバランスを保つことに繋がりました。24時間の終わらぬ育児、かつほぼワンオペという生活だったので、仕事があるおかげで一人の時間を創れたことにより、子どもと接する限られた時間を大切にしよう、愛情をたくさん注ごう、と穏やかな気持ちで向き合えるようになったんです。
もちろん、夫との協力体制も不可欠でした。朝の登園は夫、お迎えや急な呼び出しは私、というように役割分担を明確にしました。また、自治体のファミリーサポートや病児保育施設、ベビーシッターなど、使えるサービスはすべて事前に登録して、いざという時に備えていました。
完璧主義を手放し、自分らしいキャリアを築く。「キャリア=人生そのもの」
――復職を機に、仕事への向き合い方に変化はありましたか?
瀬川: はい、復職してすぐに「今まで通りにはいかない」と痛感しました。自分の体調が悪くても子どもを迎えに行かなければならないし、家事も完璧にはこなせません。そこで、良い意味で自分に期待するのをやめました。
仕事においても、限られた時間で成果を出すためには、すべてを完璧にこなすのは不可能です。他の社員と同じようには働けないという現実を受け入れ、「今の自分にできること」に集中するようにしました。
――キャリアに対する考え方も変わりましたか?
瀬川:大きく変わりましたね。以前は出産・育児期間を“ブランク”だと捉えてしまう自分がいたのですが、「キャリア=人生そのもの」と考えるようにしたんです。そうすると、育児もまた一つの役割を持ったキャリアであり、自分は常に成長し続けているんだと思えて、気持ちがすごく楽になりました。
時間の制約があるからこそ、タイムマネジメントやマルチタスクのスキルが格段に上がったと感じています。「今の自分だからこそできること、会社に貢献できることは何か」を考え、行動する。そうやって視点を変えたことで、焦りやストレスが減り、仕事に前向きに取り組めるようになりました。
朝7時始業も!フルタイム勤務を支える「柔軟な制度」と「個々の工夫」
――瀬川さんはフルタイム勤務とのことですが、時間の使い方はどう工夫されているのですか?
瀬川:会社のフレックスタイム制度を活用しています。コアタイムがなく、朝7時から15時までといった働き方ができるので、子どもの急な発熱があってもすぐにお迎えに行けました。また、勤務時間中一度退勤し、子どもを寝かしつけた後の20時からまた2時間働く、といった「私用外出制度」も活用しています。本当に柔軟な働き方をさせてもらっています。
山中:朝7時から働き、家庭内のタスクもこなし、お子さんの体調管理も徹底する瀬川さんの働き方は、本当に素晴らしいと思います。なかなかできないタフな働き方でもありますね。
松尾さん(以下敬称略):まさにその通りです。瀬川の働き方は「鉄人みたい」で、正直「レアキャラ」だと思っています(笑)。だからこそ、経営陣からは「彼女の働き方は当たり前ではない。産後の働き方は人それぞれ、様々でいい」と繰り返し社員達に伝えています。
後に続く社員がプレッシャーを感じないようにするための配慮ですが、一人に負担をかけないという会社の想いでもあります。
制度面では、コロナ禍を機に現場の声を吸い上げて、急ピッチで整備しました。経営陣にも「社員が働きやすい環境を」という姿勢が根付いており、実態に合わせて制度を柔軟に変えていく文化があります。瀬川のように実際に使いながら改善提案をしてくれる社員がいることで、会社全体の働きやすさが進化しています。

――制度だけでなく、ご自身のルーティンや工夫されていることもありますか?
瀬川:子どもの体調管理には特に気を遣っています。保育園から帰ったらすぐにお風呂に入れる。少しでも体調が悪そうな時は、悪化する前に早めに病院に連れて行く。フレックスで15時に退勤できれば、その足で病院に寄ることも可能です。
また、有休が足りなくならないように、残業した時間分を代休として充てられる「代休制度」も活用しています。他にも「時間休」など、会社の制度をフルに使いこなしながら、家庭の状況に合わせて柔軟に対応することで、なんとかフルタイム勤務を続けられています。
成長を支える1on1。聞くだけで終わらせないマネジメント
――復職と同時に新規事業のリーダーを任されたとのことですが、不安はありましたか?
瀬川:復職前面談で、上司から働き方の意向を丁寧にヒアリングしてもらえたのが心強かったです。元々いた部署に戻ると思っていたのですが、「オンラインでできる業務」「これまでの経験を活かせる」といった観点から新規事業への異動を提案してくれました。
自分のキャリアプランと会社の方向性がマッチしたことで、不安よりも「頑張ろう」というモチベーションが勝りましたね。
山中:お話を伺っていると、社員の皆さんの「やってみたい」という自発性を尊重する文化が根付いているように感じます。
松尾:そうですね。社員の自律意識が非常に高いです。最近も、運営担当の社員から「営業も学んでみたい」という声が上がり、現在、運営と営業を兼務する体制を整えています。部下の長所や強みを生かしながら、本人の意欲を尊重し、挑戦できるリソースを作る。それが個人の成長と会社の成長に繋がると考えています。
瀬川:私も入社当初はイベント運営がメインでしたが、前職の経験も活かしていずれはマーケティングを続けたいという軸を持っていました。そのため、イベント運営の部署にいた時から自分から視聴率やアンケート回答率の分析を提案し、マーケティングの要素を業務に取り入れていきました。
山中:瀬川さんのように自発性の高い方が活躍できる背景には、採用の工夫もあるのでしょうか?
松尾:おそらく、一次面接を社長が自ら担当していることが大きいと思います。応募者の方は驚かれますが(笑)。スキルや経歴だけでなく、会社の理念に共感し、自発的に動ける人材かどうかを最初に見極めることで、入社後のミスマッチを防いでいます。

――松尾さんは、1on1でメンバーと向き合う際に何を心がけていますか?
松尾:単なるタスク確認の時間にしないことです。普段は話しにくい悩みや課題、そして「これから何に挑戦したいか」といったキャリア形成に関する対話を重視しています。
一番重要なのは、聞いた話を行動に移すこと。 1on1で出た課題を解決したり、本人が挑戦したいと言ったことを実現するために社内調整に動いたりする。そこまでやって初めて1on1が意味を持つと考えています。
――セミナーインフォさんでは、ユニット間の異動や兼務も活発だと伺いました。これも組織の強さに繋がっているのでしょうか?
松尾:そうですね。戦略的にユニット間のローテーションを行うことで、多くの社員が複数の業務知識や経験を持つことになります。その結果、誰かが急に休んでも自然とヘルプし合える体制ができています。例えば、イベントの配信業務を中心に行っていた社員が、自身のスキルの幅を広げるために顧客対応・運営業務を兼務していたり、運営担当をしていた方で分析力が高い社員には、強みを生かせるマーケティング業務に従事いただいたりなど、ゼネラリスト的な社員が増えています。様々な業務を経験することで、多角的な視点を持った社員も多く、社員の「やりたい」という自発的な意欲が、結果的に組織全体の柔軟性と安定性を高めているんです。
経験を事業に還元する。『PLACEY』が描くDE&Iの未来
――『PLACEY』はDE&Iをテーマにしたメディアですが、瀬川さん自身の経験が事業に活きている部分もありますか?
瀬川:まさにそうです。新規事業のテーマを考える際、いくつか候補を出す際に「働く女性の支援」という切り口を提案しました。自身の経験から、同じように悩む人たちに有益な情報を届けたい、働きやすい社会づくりに貢献したいという想いが強かったんです。
イベント後に「大変参考になった」「勇気をもらえた」と言ってもらえる瞬間が、原動力になっています。
――会社としてDE&Iを今後どのように広げていきたいですか?
松尾:大企業ではDE&Iという言葉が浸透しつつありますが、まだまだ中小企業での課題は多いと感じています。だからこそ、『PLACEY』を通じて良質なコンテンツを無料で提供し、多様な働き方や先進的な企業の取り組みを発信していくことに大きな意義があると考えています。
社内においても、制度があるだけでなく、それを活用しながら社員一人ひとりが自分らしくキャリアを築いていけるよう、これからも現場の声を大切にしながら環境をアップデートし続けていきたいですね。
おわりに:キャリアを諦めない選択肢を
今回のお話から見えてきたのは、個人の努力と、それを支え、後押しする企業の制度・文化が両輪となって初めて「キャリアを諦めない働き方」が実現するということでした。最後に、お二人から読者の皆さんへメッセージをいただきました。
瀬川さんより(育児とキャリアの両立に悩むママへ)
私が大切にしているのは、「一度きりの人生だから、悔いのないよう自分が納得できる選択をしたい」という思いです。そのためにも、自分で選択することを常に意識しています。子どもとの時間はとても大切ですが、子どもには子どもの人生があり、私には私の人生がある。いずれ子どもも成長して自立していくからこそ、自身の成長にも時間を使いたいし、両立しようとするその努力は数年後に必ず実を結ぶと信じています。
仕事と育児の両立は、正直、楽ではありません。泣きたくなる日もあります。それでも前へ進む力は、「自分に素直でいること」。そして、「できないこと」にフォーカスするのではなく、ギブアンドテイクの精神で今の自分だからこそ出来ること、役割、やりたいことを見つけ、自己成長と会社、そして社会にプラスになることを考えることだと思っています。また仕事と育児を両立するうえで、感じたことや見直した方が良いと思ったことは正直に声を上げる、情報を集めることも大切です。
そうした小さな一歩の行動こそが、新しい選択肢を生み出すきっかけになります。
選択するためには、まず選択肢を知ることが大切です。どんな選択肢が待っているか。一歩踏み出すだけで、きっと見える世界は大きく広がります。
松尾さんより(企業の人事担当者・管理職の方々へ)
育児中の社員が声を上げたとき、それを単なる「個人の不満」と捉えず、まずは真摯に話を聞いてみてほしいです。特に中小企業では、経営層も知識や経験が不足していることが多いです。声を上げてもらわなければ、会社は課題に気づくことすらできません。まずは声を上げてくれる社員がいることに感謝が必要だと感じます。
私たちの経験からも、社員が「新しい働き方を試したい」と一歩踏み出して声を上げてくれることこそが、制度整備の推進力でした。
上がってきた声を「聞くだけ」で終わらせず、会社に働きかけることが、結果的に従業員満足度を高め、より良い会社づくりに繋がります。
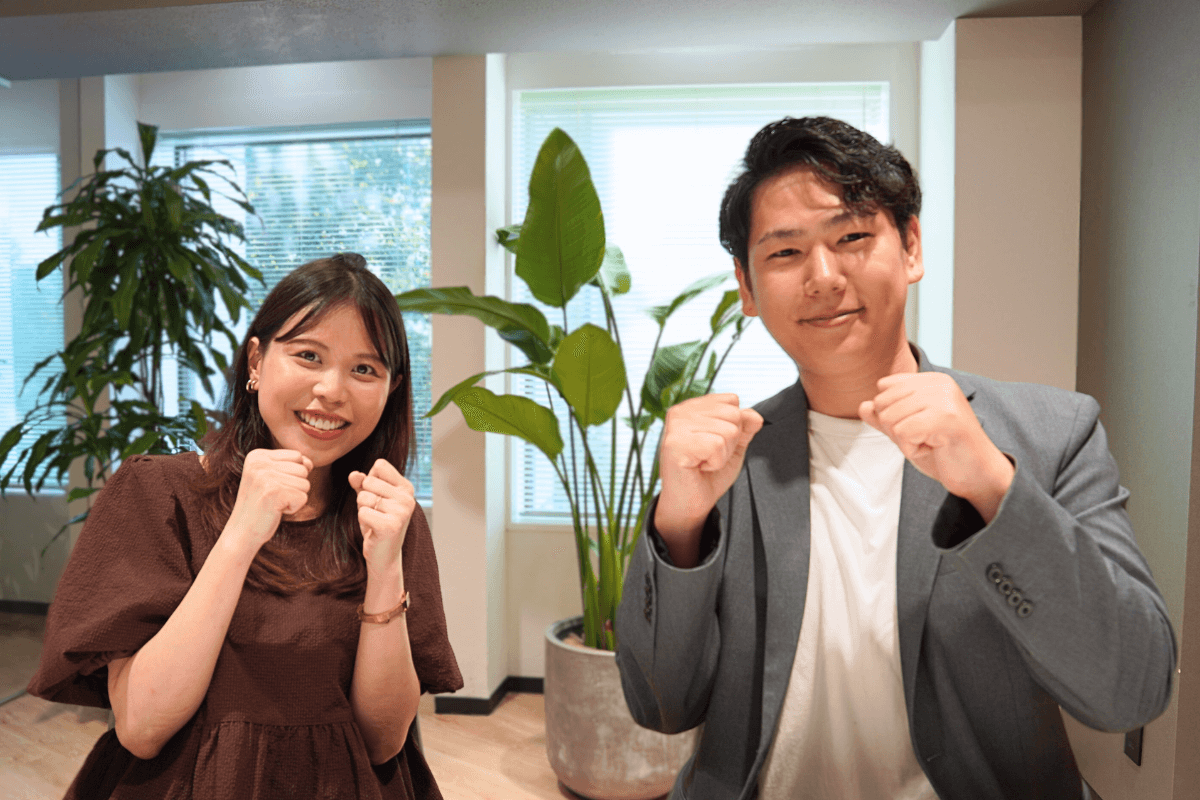
編集後記
お二人の言葉を通じて見えてきたのは、制度そのものではなく、それを活かす人の関わり方が働きやすさをつくるということでした。
どれだけ柔軟な仕組みが整っていても、誰かの理解や対話がなければ、ただの“ルール”にとどまります。
セミナーインフォでは、瀬川さんのように自ら声を上げる社員と、松尾さんのようにその声を受け止め、形にしていく上司がいます。制度は「守られるため」だけのものではなく、お互いがよりよく働くために使いこなしていくもの。そのバランス感覚と、現場での対話力こそが、同社の「働きやすさ」を本物にしているのだと感じました。
この記事が、働く人とすべての企業にとって、制度を“働きやすい環境”に変えていくヒントになれば幸いです。
『PLACEY』多様な働き方を映す場としての動画メディア
セミナーインフォが運営する『PLACEY(プレイシー)』は、「PLACE(居場所)」と「Diversity(多様性)」を掛け合わせた造語から生まれた、DE&I・女性活躍・多様な働き方をテーマにした動画メディアです。
前身となる『Lykke(リュッケ)』での発信をもとに、“一緒に創る、働く人の新しい社会。” ”すべての価値観を受け入れる”をコンセプトに2025年3月にスタート。
働く女性や管理職、DEI推進担当者、人事担当者など、幅広い立場のリアルな声を動画で届けています。
企業の取り組みや働く人のストーリーを通して、「多様な働き方のヒント」を社会に発信するプラットフォームとして注目されています。
PLACEY公式サイトはこちら: https://placey.jp/
『TUMUGU』ライフステージに寄り添う福利厚生サービス
QOOLキャリアが運営する『TUMUGU(つむぐ)』は、妊活・子育て・介護・更年期など、
一人ひとりのライフステージに寄り添いながら支援する福利厚生サービスです。
ライフイベントに合わせた専門家相談やセミナーを提供し、従業員一人ひとりの「いま」に寄り添うサポートを展開しています。
社内に相談窓口がない企業でも、“外部の伴走者”としての支援が受けられる仕組みが特徴です。
また、制度設計を整えたい企業へのサポートも充実しており、
導入企業では「働きやすさ」だけでなく「働きがい」向上にもつながっています。
TUMUGUサービスサイトはこちら:https://tumugu-service.jp/



